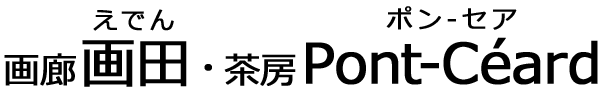●終戦記念日の今日。今年はオリンピック開催と重なるために大戦関係の特番が少ないが、「新たな文書や日記が発見された」・・・・・・なんぞと銘打ったさも戦争の真相に迫るようなタイトルの番組でありますが、果たしてそうなんでしょうか。下記の文章(証言)は、「日本海軍400時間の証言・NHKスペシャル取材班・軍令部参謀たちが語った敗戦」(新潮文庫・単行本初版は2011年7月)のなかの「神風特攻隊」に関するものです。帯には「エリートが国家を滅亡させた・日本組織の本質的問題点を抉る渾身のノンフィクション」とあります。この証言の肉声テープは1980年から1991年まで、131回にわたって、ほぼ毎月、海軍士官のOB組織である「水交会」で開かれていた、秘密の会議を録音したものである。総計4百時間の議論である。メンバーの多くが、太平洋戦争当時、軍令部や海軍省に所属していたエリート軍人。テープの保管者は反省会の幹事役であった土肥一夫氏。
「最後の最後に語られた「特攻」『特攻。特別攻撃。これについて、特別攻撃の発端と申しますか。皆さんもみんな故人になれて、私がみなさんに申しあげて記憶しておいて頂きたいと思うのですが』『昭和十九年のこれは十月・・・・・・(略・本文)大西中将ですね。それまでは軍需省に勤務されておったんですが、昭和十九年の十月の初めに軍需省を辞めさせられて、そうしてフィリピンにおります第一航空艦隊の司令長官に補職される事に相成ったんであります。第一航空艦隊の司令長官に。そうして、大西さんの任地に出発せらるる前に、軍令部にお出でになって、そうして軍令部の軍令部総長官舎。今の日比谷のあれ、家庭裁判所ですかね。あそこの所に軍令部の総長の官舎があったんですが、その所の二階に時の軍令部総長の及川大将、そうして次長の伊藤整一中将。そして一部長の私。そうして大西さんと。この四人で会いまして。大西さんがこれだけ来てくれと。申しあげることがあると、こう言うので、それで大西さんがおもむろに口をお開きになりまして、そうして今の一般戦況、もう日本の敗戦濃厚であると。それに加えて航空兵力は機器は十分に出来ないばかりでなくて、その搭乗員の訓練不足と言いますか、訓練未熟で、到底当たり前の空中戦闘は出来かねると。
それに加えて敵は電波兵器ですね、電波兵器ができて、電波兵器で我が来航するのを察知し、それで戦闘機を高く待機させて、こちらから大きな爆弾を持っていけば、覆いかぶさってきて、みんな攻撃をする前に撃墜されてしまうと。それだからこの際、搭乗員に当たり前の空中戦闘など避けて、もっぱら敵をかわして目標の敵の航空母艦なり艦船に体当たりしろと。こうするのが一番かえって情けが深いじゃないかと。そういうような戦法をこれからフィリピンでしたならば取らせたいから、ご承知を願いたいと。こう言って大西さんからそういうような意見具申が出たんであります。』
『その時に私は体当たりという事は考えておりませんし、もちろん命令などを出した事はありませんので、それでややしばらく四人は静思黙考、声なしとこういうような情勢だったんでありますが、そうしてややしばらくして、及川軍令部総長が、口を開かれて、大西君、あなたの言われる事はよくわかりました。しかし大西君、命令だけではやってくれるなよと。それが私は今でも印象に残っております。命令だけではやってくれるなよと。各搭乗員の発意によってそれでやるというのならば、それでやってくれもよろしいと』
そして特攻作戦に関する、自らの責任について語ることはなかった。
『私も軍令部の作戦部長としておったんですが。特攻というのは、これは作戦ではないと。作戦というのは、命令、服従。これらの関係で、やるので、お前その行って死ね、とこういう事を命令するというのは、作戦に非ずと。作戦よりももっとデグリーのオーダーの高い崇高なる精神の発露であって、作戦に非ずと』」(pp189~191)
この証言のテープに張られたタイトルは「昭和52年7月11日 定期公演会 中澤佑氏(海軍時代の回想)」。この講演はここで終了しているのだが、その後の質疑応答で、妹尾作太男(せのおさだお)という海軍兵学校七十四期卒業の人が演者の中澤佑元中将へ「人間爆弾」について質問したところ、中澤氏自身はその作戦立案など一切に関与してないと断言し、かつ部下が独断専行したものだと言って、会場に参加していた元部下に話を振った。が、テープに元部下の発言はなく、録音は会場の「笑い」で終了していた。中澤氏はこの講演の5カ月後に他界。元部下とは、同じ軍令部の土肥元中佐。先の戸高氏は、その後に土肥氏から質疑応答の続きを聞いており、元上官の中澤氏から話を振られた土肥氏はその場で『いや、私は特攻関係の書類を持っていって中澤さんのハンコをもらいましたよ』と答えたという。(pp191~196をまとめた)テープは故意にカットされたということか。
この人間爆弾とは、当時海軍部内の秘匿名称で「マルダイ」と呼ばれた「桜花」のこと。軍令部は陸軍の参謀本部に相当。
大西滝治郎元海軍中将(1891~1945)は、フィリピンにおけるレイテ沖海戦で特攻作戦を指揮し、その責任から終戦翌日の8月16日に国内で自決した。特攻作戦の是非には両論あり、特攻攻撃された米軍はその決死の恐怖から、本土決戦を避け、早期の終戦を模索したともされる。
「新たな証言や記録、日記が最近発見された」という、それも戦後71年も経っての今にだ。上の証言などからして、当時作戦立案実行に関与した海軍軍令部総長を含む最高幹部らが、終戦後30年以上経過しても、嘘をつき自身の責任逃れをし、ましてや部下に責任を押し付けている(責任転嫁)ことである。部下は死ぬまで部下であり、上官に逆らう事はできなかったということである。歴史の真相はこのメカニズムで封印され続けてきたし、これからもその可能性があるということだ。
いちばんの許せなく腹立たしいのは、戦地に行くこともなく戦況を正しく把握することもなしに作戦立案し、それを最前線に命令した軍令部の高官が、終戦となるや貝のように口を閉ざし、無謀極まる作戦の立案や指揮命令を最前線の将・佐・尉官の独断専行として責任転嫁したことにある。最前線の指揮官や特攻で敵艦に突っ込んでいった隊員たちの無念さははかり知れない。まさか、自分らの上官が戦後、戦争の真相を自ら捻じ曲げ、責任をも部下の責任として押し付けようなんて想像だにしたであろうか。これじゃ、死人に口なしであり、家族や国のために自決した彼らの霊は浮かばれようがない。戦地に一度も赴くことなく、軍令部本部で決死無謀の作戦を立案し、戦後は、自身らの責任回避にひたすら傾注し続けた軍令部参謀たちのエリート集団。多くの戦死者たちの英霊を背に、戦後、彼らはなにくわぬ顔でそれぞれが社会の要職に就き、軍人階級に相応の生活をしてきたのであろう。これが戦争であり、いつの時代も強者弱者の必然の形であると言ってしまえば元も子もないが・・・・・・果たしてそれで彼らを許せますか。
余談ながら、宮崎市出身(宮崎郡住吉村)で当時19歳の永峰肇(ながみねはじめ)海軍曹長(最終階級)は、最初の特攻隊員に選ばれた5人のひとりである。選ばれたというのは志願していないということである。大西滝治郎中将が発案したとされる神風特攻隊の関行男大尉率いる「敷島隊」に所属。1944年10月20日に出撃したが悪天候のため敵艦を発見できず帰還。その後も毎日、出撃するも叶わず、結局は25日に護衛空母「セント・ロー」に特攻して撃沈させたとされる。死没地はフィリピンレイテ島タクロバン沖。この戦果によって、特攻作戦は正式な作戦とされ、終戦まで継続された(※)。永峰肇の両親は偶然見ていたニュースで彼の死を知ったと云う。彼の辞世の句は「南溟(海)に たとへこの身が果つるとも いくとせ後の春を想へば」。この句は、出撃を繰り返して何度か帰還した機体内部に彫られていたもので、整備兵が紙に写し取って、両親へ送付した。彼の辞世の句は、宮崎神宮の護国神社と赤江の宮崎特攻基地の慰霊碑に刻まれている。レイテでは約500が特攻したとされる。敷島隊と永峰肇に関しては、2014年1月号の文芸春秋で紹介されている。
※宇垣纏(うがきまとめ)海軍中将は8月15日正午の玉音放送直後、大分から16名を引連れて特攻し、彼らを犠牲にしたとして非難された。