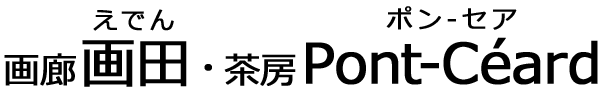人間の外科医療の専門は、例えば食道癌を手術する場合、消化器外科か胸部外科が担当する。心臓のバイパス手術は心臓外科か、循環器外科、あるいは心・血管外科が受け持つだろうが、胸部外科の看板では食道癌や肺癌などの手術が専らであろう。最近では乳癌だけに特化した病院もあるが、現在の医療の分科は消化器や呼吸器、循環器など解剖や機能(生理)的に近い関係にある臓器別か、頭・頸部外科や口腔外科などの部位別に分かれる。
犬猫の外科の場合は大きく2つに分かれる。一つが軟部外科で、もう一つが整形外科である。骨折や椎間板ヘルニア、離断性骨関節症や前十字靱帯断裂などの関節内や、膝蓋骨脱臼症や股関節形成不全などの先天的疾患の整復など、異常な骨と関節を手術で整えるのが整形外科である。軟部外科は避妊や去勢、腫瘍全般など骨や関節に直接触れない手術である。
アメリカの獣医大学ではSOFT TISSUE(軟部外科) と ORTHOPEDICS(整形外科)の2科に分かれ、日本でも最近、一部の獣医大学でその傾向にある。内外の開業獣医師の99%は通常どちらもやってのける。
最近、ある獣医関係の小冊子に東大の佐々木伸雄先生が「整形外科の今、これから-獣医療において整形外科はどう発展してきたのか? そして未来は? 整形外科の「これから」について考える-」と題して寄稿している。小生も最近、常々に同じような感触をもっていたので、その一部を紹介しよう。
1.「骨折の整復法」では、「・・・ただ、創外固定法はインプラントの多くが創外にあり、感染の可能性を完全に排除することができない点を考えると、個人的には、創内での確実で容易な固定法がより多く開発されるのではないか、と考えている。」とある。
2.「股関節異形成」では、「・・・数年前に、本症に関する予後調査を行い、骨盤3点骨切り術と保存的治療を行った症例のその後の症状の回復、調査時点での運動機能、は行のレベル、飼い主の満足度等について検討した。その結果、55頭の調査可能な症例の中で、5年以上(最長で10年以上)経過した症例においても、80%以上の飼い主が、その時点での運動機能について満足とする結果が得られた(3点骨切り術症例と保存的治療症例の間に有意差なし)。我々が実施している保存的治療は、疼痛の強い時にはNSADsの投与を行うが、その間であっても、運動を必ず継続する。・・・・・使役犬のように強い運動を日々行わなければならない場合、人工関節の適応ではあろうが、いわゆる家庭犬においては、保存療法も良い選択ではないかと思っている。」とある。
3.「前十字靱帯断裂」では「・・・また関節外法によって機能回復が見られる点から、膝関節の安定性が、関節包の肥厚や拡張した関節包の収縮によって達成できることを示しているが、・・・・・」とある。
1の創外固定法は四肢や下顎骨折などで皮膚などを切開することなく、ピンを骨の長軸に対して垂直に串刺しにして外部を螺子(らし=ネジ)やセメントで固定するものである。骨折は、いかなる方法であろうと骨折端の動きを一定の期間阻止できれば癒合する。見た目や、短毛種の場合の搬痕、それに佐々木教授が指摘するように感染の問題がある。
2の股関節異形成(股関節形成不全)は遺伝的素因が強い大型犬の疾患である。股関節が形成される7~8か月齢までの肥満や過度の運動、カルシウムの過剰摂取などを回避すれば、発症を著しく抑えることができる。骨切り3点術は10~15年ほど前によく流行った手術である。股関節の寛骨臼に大腿骨骨頭が十分に深く入るように、骨盤の3か所を切断して角度を変え、その形でプレート固定するという、複雑で厄介な手法である(ヒトの整形手技の模倣)。非ステロイド系の消炎・鎮痛剤(NSAIDs)とグルコサミンやコンドロイチン硫酸、ヒアルロン酸などのサプリメントを併用した内科療法が、長期の予後調査で外科療法と大差ないということは、痛い目に合わなくて済む点で、外科手術に優る。
3の前十字靱帯断裂の術式は、獣医外科の疾患別術式数でおそらくトップであろう。日本では約25年前から本疾患が認知され、術式はアメリカの方法が請売り的に汎用された。当初は自己皮膚や大腿筋膜を細長くトリミングして関節内を通し、靱帯の代わりをさせる方法が主流であった。最近は膝関節の関節包を切開して、断裂した靱帯を除去し、半月板の異常を確認するが、関節内に靱帯の代替物を通すことはしない。関節包を縫合した後は、関節外に大きめのナイロン糸などの人工材料で靱帯の代わりとするのが一般化している。現在の手技は当初の方法に比べてかなり簡単である。また、以前は5kg以下の小型犬でも手術を実施していたが、1週間程度のケージレストで歩行が可能となる症例も少なくない。10kg以下の個体でも保存療法が功を奏する場合もある。
今回は獣医外科学の進歩について講釈を垂れてみた。椎間板ヘルニアや骨盤骨折、指骨骨折など必ずしも手術をしなくてもよい症例が多いと感じる、最近である。膝蓋骨脱臼の手術適応は既に制限された疾患と考えられる。椎間板ヘルニアは、突出する椎間板の速度と量によって脊髄の損傷度合が決まる。深部痛覚と自力排尿があれば早急に手術に踏み切る必要はない。1週間のケージレストとその後の懸命なリハビリで歩行可能になる症例が殆どである。後躯が萎えたならば、脊髄の炎症を抑制する注射薬を出来る限り早めに投与することが重要である。ダックスフントの飼い主にはこの点を普段より啓蒙しておくと良い。10頭中8~9頭が椎間板ヘルニアで来院する現在において、手術適応基準なるものを作成しないと、無用の手術が行われる可能性が高い。骨盤骨折は、直腸検査をして骨盤腔の狭窄がなければ徹底したケージレストで手術を避けるケースも少なくない。中手骨や中足骨、指骨も外固定で患肢を全く使わせない状態を保てば、2本以上の骨折であっても手術の必要がないケースも多々ある。4本肢の動物は2本である人間とは相当に違うことを、もう少し早く気づく必要があったのである。犬では前肢に7割の体重が、後肢に残りの3割がかかる。解剖学的に同じような病態であれば、何でも彼(か)でもヒトの真似をして手術という発想自体が、悪の根源なのである。