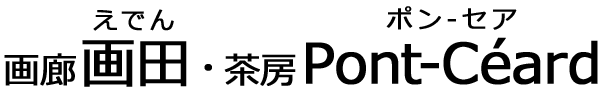「すし」は「酸(す)し」といい、大辞泉によると、①「塩をふった魚介類を飯とともに漬け、自然発酵によって酸味を生じさせたもの。熟(な)れずし。生熟れ。」、②「酢で調味した飯に、生、または塩や酢をふりかけた魚などの具を配した料理。握りずし・散らしずし・蒸しずしなど。酢は暑さに耐えるので夏の食品とされた。」とある。
分り易くすると、酢・塩に漬けた、すなわち酢あるいは塩で〆た魚が「鮓」であり、魚を調理・調味して旨さを引き出したものが「鮨」である。「寿司」は当て字。
保存の手法が旨みをひきだしたところが、なんともオモシロイ。正しく天の恵みである。
握り鮨のルーツは江戸の「華屋与兵衛」までさかのぼる。華屋与兵衛(1799-
1858)が最初に握り鮨を考案し、握ったのは1820-1822年頃だと言われる。山葵を最初に使ったのも与兵衛である。華屋与兵衛の功績は国民栄誉賞、いや文化勲章ものだ。
与兵衛は今も当時もであるが「煮ても焼いても、生でも食えないコハダ」を酢で〆て、掌の酢飯の上にのせ合わせて握る方法(調理法)を考案した。現在の握りずしの本家本元であり、当時は東京湾(江戸前)の魚介を使ったことから、「江戸前鮨」と言われるようになった。現在も東京風の握り鮨を「江戸前鮨」と呼んでいる。
「二束三文(薪の束)」または「二足三文(こちらは草鞋=ワラジのこと)」という言葉があるが、これは安価であまり長持しないものの喩えであろう。当時、与兵衛が握る鮨は1貫(個)250文もしたという。一文が現在の貨幣価値で25円(諸説あり。当時「四文屋」というのがあり、今風だと100円ショップや100円回転寿司に相当するから、1文=25円が覚え易い=これは小生の全くの私見)というから、当時の250文は6250円となり、ちょっとした何とか料理のフルコースに匹敵する。あまりの高値から老中・水野忠邦(1794-1851)が行った天保の改革(天保12-14年=1841-1843)の倹約令に抵触したとして、与兵衛自身投獄された。高値で贅沢だということで「お縄」であるから凄くて怖い。1824年に屋台で開店した「与兵衛鮨」は1930年(昭和5年)に閉店している。
江戸時代の江戸前の鮨ネタとしては、コハダ(小鰭)が代表だ。鰭はヒレまたはハタと読み、魚のひれを意味する。「鰭(はた)の広物」とは「ひれの広い魚。大きい魚。⇔鰭の狭物(さもの)」のことを言う。「小肌」とも当てる。
「コハダの仕事ぶりで、どんな鮨屋かわかる。」と言われるほど、鮨屋にとっても客にとっても、最重要で貴重なネタである。酢と酢飯との相性が抜群で、皮が薄いのも好まれる理由だ。塩と酢で〆た「シンコ」に至っては3~4個を束ねてサビ無しでそのままか、「煮キリ」をチョビリとつければ昇天の気分である。この魚は鰤(ブリ)などと同じく出世魚であり、関東では10cm以下の幼魚をシンコ(新子)、10cmを超えるとコハダ、15cmになるとコノシロという。東京湾のコハダが有名で、養殖はないが、台湾や東南アジアからの輸入物あり。
江戸期のコハダ以外のネタは、アジ、イカ、タコ、ハマグリ、アナゴ、キス、サヨリなどが主でいづれも生ではなく、酢〆、あるいは加熱調味したものであった。
コハダと双璧の鮨ネタはマグロの赤身である。江戸期のマグロはサツマイモ、カボチャと並ぶ下下の食い物であり、それも腹身のトロは田畑の肥やしか、「目黒の秋刀魚」ではないが、長屋の庶民が焼いて食していたと言う。赤身も他と同じく生ではなく、「ヅケ」で握られていた。「ヅケ」とはマグロのサクを醤油と味醂に漬け込んむが、その調合や時間などの手法は店でかなり違う。現在では切り身を数十秒漬けて、それから握る鮨屋も珍しくない。
小生も「鮓」・「鮨」をコヨナク愛して止まない人間の一人である。
みやざきは海・山の幸が豊富と言い切るヒトが多いが、果たしてどんなネタで鮨が握ってもらえるのだろうか、検証してみよう。
まず何といっても「コハダ」である。銀座の名店「すきやばし次郎」の小野二郎氏は九州産も使う。8月~9月には有明海や太良町(たらちょう)産の「新子=シンコ」も堪能できる。この「コハダ」・「シンコ」をみやざきに直で仕入れなくてはならない。
「コハダ」以外の「光もの」であるアジ(鯵)とサバ(鯖)は、大分のお世話になろう。言わずもがな、佐賀関の「関アジ」と「関サバ」である。福岡のサバも侮れない。鹿児島の阿久根のサバも遜色なかろう。九州(西日本)人ならイワシ(鰯)はマイワシ(真鰯)ではなく、門川獲れのウルメでまいろう。
関サバ・関アジは直球勝負で、生で握ってもらおう。阿久根のサバは皮と2~3mmの身が仄かに変色する程度に塩で〆、酢にさっと潜らせる。少なくとも8割の身は、鮮紅色でないと旨くない。福岡サバは仕込んで一晩じっくり寝かせたものにしよう。内海の肥ったマアジも捨てたものじゃない。一品もので「なめろう」も頂こう。門川獲れのウルメイワシは注文をしてから手開きしてもらい、下ろしショウガを載せてもらおう。
意外と知られてないが、寒の日向灘獲れのブリも流涎ものだ。
マグロは勿論、油津の本(クロ)マグロで決まりだ。トロと赤身、ヅケも頂かなくてはならない。本マグロが仕入れ困難の場合は、ミナミ(インド)マグロで文句は言えない。冷凍技術の進歩で冷凍マグロの方が旨い場合も多々あるから嬉しい。
赤身ももう一つ欲しいところだ。青島のもどりガツオでどうだ。。下ろしショウガと葱を載せてもらおう。
白身は日向灘獲れの本カワハギで、濾した肝にモミジオロシと葱をさり気無く載せてもらおう。この手の技は、小生が最も尊敬する鮨職人で、銀座8丁目・並木通りに店を構える「小笹すし」の店主・寺嶋和平氏に教えを仰ごう。
キスと平目の昆布〆も握って貰いたい。日南獲れのクエ(ハタ科、九州ではアラと呼ぶ場合あり。本アラはスズキ科)はサクで1~2日寝かして旨み成分が溶出したものが良かろう。白身の極みは、ヤガラ、カサゴの生でいこうか。試しに日向灘獲れの高級魚「オコゼ」も(夏魚だが)握ってもらおう。
煮物は北浦獲れのアナゴ(マアナゴ)と日向のハマグリ(蛤)、特にハマグリは最高物だ。アナゴは料理人の知恵でフワフワと柔らかい、口の中で蕩けるものにしてもらおう。アナゴの「雉(きじ)焼」も一品もので拵(こしら)えてもらおう。ハマグリは日本一だから、旨くなければ料理人は失格だ。吸い物や焼いてでは甚だしくモッタイナイ。「(煮)ツメ」も超一級の味とトロミ、それに艶が必要だ。煮ハマグリには、日向の平兵衛酢を一滴垂らそうか。
軍艦ものは、都農のウニで十分に潮と藻の香を堪能できるであろう。海苔は大分産も有るが、これも日本一の有明海苔でないと拙(不味=まず)かろう。串間・都井岬のトビウオの「トビッコ」(ゴールデン・キャビア)も見逃せない。イクラは急速冷凍技術の進歩で日本中どこで食しても同じ味が一年中堪能できる時代だから、心配無用だ。マイナス50度での保存なのでディープ・フリィーザー(deep freezer)が欠かせない。極みは川南産の旭蟹の身に蟹みそ(肝臓と膵臓)を載せてもらおう。
「みやざき鮨・十貫」のネタはまだまだ沢山有りそうだ。一方で、ネタと一体の「シャリ(舎利)」はどうしよう。「アガリ」と「ガリ」も県産に拘(こだわ)らないといけない。巻ものは「レタス巻き」に習った新メニューの発案・考案にも労したいところだ。
検証すれば、銀座や築地でなくとも、旨くて結構安い「江戸前鮨」が食えそうであるから、考えるだけで楽しい・・・・・が・・・。無性に銀座八丁目の「小笹寿し」の鮨が喰いたくなってきた。流涎、流涎、流涎・・・。食材調達や手間(仕込み)の労苦を惜しんでは、旨い鮨は出来ない。アソビ心も必要だ。みやざきの海の幸を自在に操った鮨を堪能できる近未来を信じよう。